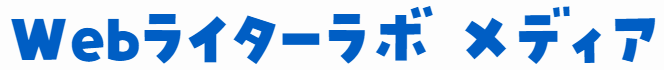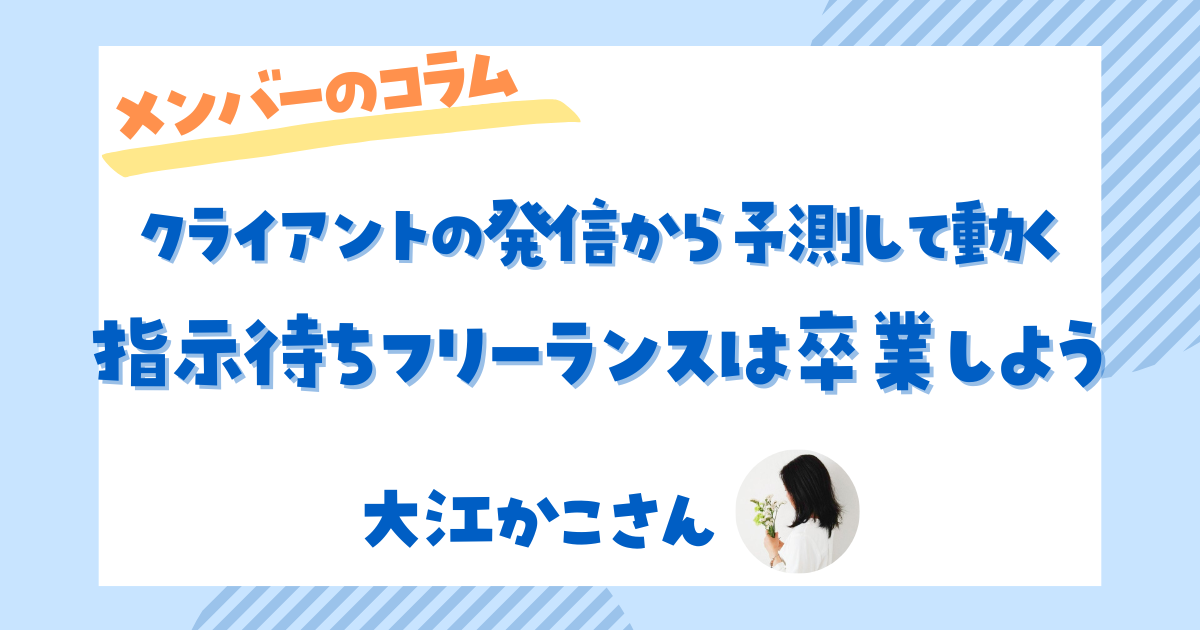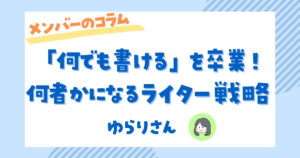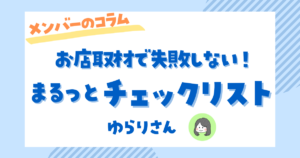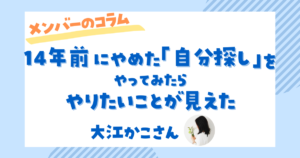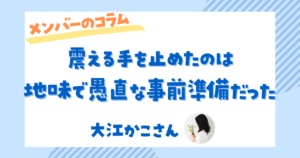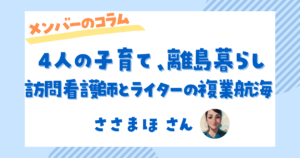はじめに
Webライター向けオンラインコミュニティ「Webライターラボ」では、所属しているメンバーがコラムを書く企画があります。
今回紹介するのは、運営統括の “大江かこ” さんの連載コラムです。
「暗黙知の共有」を得るために、クライアントの発信をリサーチする
フリーランスになってから、クライアントの発信をリサーチするのが、私の日課になりました。チェックしているのは、Xの投稿、音声配信、YouTube、noteの記事などです。
私がクライアントの情報を毎日チェックしているのは、「暗黙知の共有」を得るためです。「暗黙知の共有」とは、目や耳から入ってくる断片的な情報から、空気や文脈を読むこと。会社で働いていた頃は、オフィス内で見聞きした情報を元に、先回りして仕事を進めるときもありました。
でも在宅で仕事をするようになった今は、チャットツールやメールでのやり取りが中心です。自分が担当している業務の相談や報告がほとんどなので、このままだと仕事の質は上げにくいなと感じました。
「指示された業務をやればいい」「余計な情報はいらない」のような考え方もありますが、それだと自分も仕事を楽しめません。そこでクライアントの情報を毎日チェックして、自ら「暗黙知の共有」を獲得しようと考えました。
情報を活かして先回りすると、急な依頼に焦らない
クライアントの発信を見聞きしていると、軸になっている考え方、今進めている仕事、今後やりたい事業、などが分かります。私がやっているオンライン秘書の仕事では、急に仕事を依頼されるケースも少なくありません。
日頃からクライアントの発信に触れていると、脳内に薄い記憶として残ります。多分、この時点で心の準備ができるのでしょう。しばらくしてから、急な仕事の依頼をもらったとしても「前にYouTubeで話していたアレのことか」と思い出せるので、「急な依頼」とは感じにくいです。
また、場合によっては、先回りして準備したり、サポートの提案ができたりもします。
私は営業事務として企業で働いていたとき、同じチームのマネージャーや営業担当をよく観察していました。さまざまな情報から、やるべき仕事が予測できれば、急な依頼にも焦らないと気がついたからです。
たとえば「100人が参加するセミナーの開催が、12月10日に決まった」と、営業担当がマネージャーに話している様子を見たとします。私はそこから、自分が依頼されそうな仕事を予測していました。
会話を聞いただけで、着手できる作業は少ないですが、「資料を準備する仮スケジュールを考える」「封筒や用紙の在庫を確認する」くらいはできます。
少し準備をしてから営業担当に「セミナーの日程、決まったんですか?」と声をかけると、話がスムーズに進む場合が多いです。仮スケジュールはその場で摺り合わせられますし、封筒や用紙の発注も余裕を持ってできます。
このように指示を待って動くより、「暗黙知の共有」を活かして自分から行動した方が、メリットは多いです。余裕を持って準備を進められるので、営業担当にも安心してもらえます。
営業事務時代にやっていた「暗黙知の共有を活かした働き方」は、フリーランスになった今でも、役に立っています。
メルマガやSNS運用代行の仕事では、クライアントの文章を完コピする
ライターやSNS運用代行の仕事でも、「クライアントの発信をリサーチしていて良かった」と思った経験は多々あります。
以前、私は経営者であるAさんのメルマガを執筆していました。Aさんが録音した10分程度の音声データを1,500文字の文章に起こすという内容です。一人称形式のメルマガだったので、本人になりきって執筆する必要があります。
私はAさんの発信を毎日リサーチしていたので、「Aさんならこんな言葉を使うだろう」、「Xで発信していた内容を追記しておこう」など、考えながら執筆できました。
また、インフルエンサーであるBさんのInstagram運用代行チームにいたときは、Bさんの文体を真似るために、ブログやInstagramの文章をWordに書き写して練習しました。Bさんは人に話しかけるような、やわらかい文章を書く人です。話し言葉で使う「食べれる」などの「ら抜き言葉」もたまに見かけたので、投稿を作るときに入れるよう意識しました。
するとある日、Bさんから「自分が書いた文章みたいです!」と感想をもらったのです。発信をリサーチしていて良かったと思った瞬間でした。
メルマガ執筆やSNS運用代行の仕事では、クライアントになりきって文章を書く場合があります。このようなときは、クライアントの発信から文章のクセ、良く使う言い回しなどをピックアップしてリスト化しておくと、記憶に定着しやすいです。リストを何度も見返すうちに、執筆時に自然と手が動くようになります。
リサーチする媒体は2つだけでOK、依頼された仕事に合わせよう
クライアントの発信媒体が、X、Instagram、音声配信、YouTube、note、ブログなど、多岐に渡る場合、全てをチェックするのは難しいです。そのようなときは、2つほどリサーチする媒体を決めてチェックしましょう。
ライティング系の仕事ならnoteやブログ、SNS運用代行ならXやInstagram、事務系の仕事なら考え方やここだけの話が出やすい音声配信、など。依頼された仕事によって、チェックする媒体を選ぶのがおすすめです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。私の連載コラムは今回で最後になります。私は「縁の下の力持ち」のような立場で仕事をしているので、仕事内容の言語化が難しいケースも多いです。でも、今回のコラムを通して、今まで感覚的にやっていた行動が言語化できました。AI時代だからこそ「暗黙知の共有」は、人間にしかできない武器になるのではと思っています。
今回のコラムが、今後フリーランスとして仕事の幅を広げたい人、仕事の質を上げたい人の参考になると嬉しいです。
さいごに
Webライターラボは「AI時代に長く活躍できるWebライターになろう」がコンセプトのオンラインコミュニティです!
興味がある方は、運営者の中村の公式LINEをチェックしてみてください。
Webライターがまず学ぶべき「ライティングの基礎」を配信しています◎
公式LINEに登録後、「文章25」と送っていただくと
「AI時代を生き抜くためのWebライティング基礎講座」の動画が自動返信されます!
筆者:大江かこ(@kakoworks1)
編集:中村昌弘(@freelance_naka)